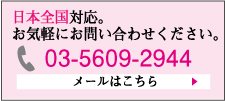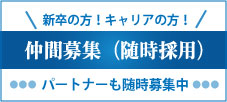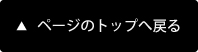経営シミュレーション”RobotS”における投資意思決定
今日はあるメーカーで実施した経営シミュレーション“RobotS”についてです。
これまで異業種交流などで実施してきましたが、今回は自動車系メーカー単独の実施でした。


経営シミュレーションの醍醐味は、参加する人たちの意思決定で、経営結果が良くも悪くもなることです。
小売業と商社で実施した幹部対象の異業種交流で実施したとき、私が実施してきた中で一番市場が拡大し4期間の経営活動としてよりよい結果、最高の数字となりました。やはり幹部になるような人は違うなあと感じていました。
ところが、、、
今回自動車メーカーでの実施は3期間で中堅クラスの若手対象でしたが、スタートからの1期、2期は、今回の方が結果が優れていました。“RobotS”は製造メーカーの経営シミュレーションなので、メーカーの人にはなじみやすいのもありますが、それでも幹部クラスになる人たちより中堅若手クラスでの結果が良かったことに驚きを隠せませんでした。
3期目は、幹部クラスの方が結果が良かったので、やはりそうなるか・・と一安心しましたが、なぜそうなったのか、この1期、2期、3期の経営活動での意思決定の違いはなんだろうか?と考えました。
私になりに振り返ると、自動車系メーカー中堅クラスの意思決定は
①メーカーのため製造原価の設定や品質管理が細かく緻密であった。ものづくりとして品質にこだわる傾向が随所に見られた
②また工場ラインの稼働をフルにするために機種選択と製造時間とのバランス、生産計画が合理的で適切であった
③情報感度も良く、売るための施策も良く練られており、販売促進、広告宣伝などの外向きの投資も積極的であった
④しかしながら現存のラインで生産効率を高める活動が中心となり、設備投資が消極的であった
ことが1期、2期の優れた結果を導き出しましたが、3期目の結果で逆転されてしまったのだと考えます。
異業種交流での幹部クラスの優れていた点は2期目、3期目の設備投資への意思決定です。幹部は中堅の方々より中長期の視点、投資に対する感度が優れています。逆に言えば、中長期の視点と投資意思決定の強さがないと幹部にはなれないとも感じました。
同時に、そうした考え方、思考を中堅クラスから啓発していくことが早期の幹部育成になるとも思えました。

コラムに対するコメントなど何なりとお寄せ下さい。
コメントはこちらから